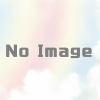能登の魚醤油(うおしょうゆ)「いしり」 〜様々な料理と良く合う独特の風味とコクのある旨み〜
日本の伝統的な調味料として醤油がありますが、魚介類を利用してその旨味を高めた醤油に魚醤油(うおしょうゆ)というものがあります。
魚醤油(うおしょうゆ)は海外ではタイの「ナンプラー」、ベトナムの「ニョクナム」がありますが、日本では能登半島の「いしり」、秋田県の「しょっつる」、香川県の「いかなご醤油」が日本三大魚醤と呼ばれ、能登半島の「いしり」は、その中でも生産量で日本一を誇っています。
今回は和食はもちろん、醤油を使う全ての料理の旨味を高める能登の魚醤油(うおしょうゆ)「いしり」を紹介したいと思います。
能登の魚醤油(うおしょうゆ)「いしり」とは
「いしり」(いしる)は、石川県能登半島で江戸時代中期から受け継がれてきた伝統的な魚醤油です。新鮮な魚や真イカの内臓に塩を加え、1年以上かけて自然発酵・熟成させることで、深いコクと独特の風味を持つ調味料に仕上がります。
能登半島の漁師町では、古くから貴重なタンパク源として、また保存食としても重宝されてきました。現在でも地元の家庭料理には欠かせない調味料として親しまれています。
能登の魚醤油(うおしょうゆ)「いしり」の特徴
- 能登半島で江戸中期ごろから伝わる伝統製法の魚醤油
- 魚や真イカの内臓をつかって自然発酵させ、熟成させることで作られる
- 様々な食材との相性が良く、料理の隠し味として最適な自然万能調味料
- うま味の元となる総遊離アミノ酸が多く、抗酸化物質、血圧上昇抑制物質も含む
「いしり」と「いしる」の違い
能登半島では地域によって呼び方が異なります。能登半島の外浦側(日本海側)では主にイカの内臓を使った「いしり」、内浦側(富山湾側)では主にイワシやサバなどの魚を使った「いしる」と呼ばれています。どちらも魚介類を発酵させた魚醤油ですが、原料の違いにより風味に微妙な違いがあります。
いしりの栄養価と健康効果
いしりは単なる調味料ではなく、健康面でも優れた効果が期待できる発酵食品です。
豊富なアミノ酸
魚介類のタンパク質が発酵・分解されることで、旨味成分である遊離アミノ酸が豊富に含まれています。特にグルタミン酸、アスパラギン酸などの旨味アミノ酸が多く、これが独特のコクと深い味わいを生み出しています。
機能性成分
- 抗酸化物質: 老化防止や生活習慣病の予防に役立つ成分
- 血圧上昇抑制物質: 高血圧予防に効果的なペプチド類
- ビタミンB群: 疲労回復や代謝促進に寄与
- ミネラル: カルシウム、鉄分などの微量栄養素
いしりの使い方・料理法
いしりは和食だけでなく、洋食や中華料理にも幅広く活用できる万能調味料です。
基本的な使い方
- 鍋料理: いしり鍋は能登の郷土料理。出汁にいしりを加えるだけで、魚介の旨味が凝縮された絶品鍋に
- 煮物: 通常の醤油の代わりに、またはブレンドして使用。魚や野菜の煮物に深みが増します
- 炒め物: 野菜炒めや焼きそばに数滴加えるだけで、プロの味に
- お浸しや和え物: 少量加えることで旨味がアップ
- パスタソース: ペペロンチーノやボンゴレに加えると、和洋折衷の新しい味わいに
- ドレッシング: オリーブオイルと混ぜてサラダに
使用のポイント
いしりは香りが強いため、最初は少量から試すことをおすすめします。加熱することで香りがまろやかになり、旨味だけが残ります。通常の醤油に数滴加えるだけでも、料理の味が格段に向上します。
保存方法と賞味期限
いしりは発酵食品のため、開封後は冷蔵庫で保存してください。直射日光や高温を避ければ、長期間品質を保つことができます。発酵調味料特有の香りの変化はありますが、これは品質劣化ではなく、熟成が進んでいる証です。
まとめ
能登の魚醤油「いしり」は、江戸時代から続く伝統製法で作られる、日本を代表する発酵調味料です。豊富なアミノ酸と独特の旨味で、和洋中問わず様々な料理の味を格上げしてくれます。健康効果も期待できる天然の万能調味料として、ぜひ日々の料理に取り入れてみてください。
初めての方は、まず少量から試して、その深い味わいと料理を変える力を実感してみてはいかがでしょうか。
▼ 人気の能登の魚醤油「いしり」をチェック ▼
能登の魚醤油「いしり」 商品一覧